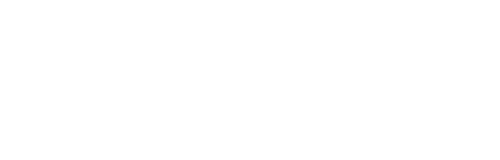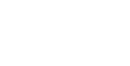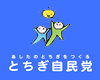2月18日に「超党派フリースクール等議員連盟」が開催されました。自分は当選してすぐに入会しましたが、その会議には下村文部科学大臣も出席され、今後、憲法26条を根拠として「(仮称)普通教育支援法」の制定に向けて、文部科学省、法制局を交えて議論を進めて行くことが決定しました。つまりフリースクール等の多様な学びが国の教育制度の中で正式に認められるということになるのです。
高根沢町の行ってきたことは間違っていませんでした。ただ、10年早かったのかも知れません。
「不登校支援の原点」
私が高根沢町長に就任したのが平成10年の8月です。「手間、暇かけて」を合言葉に、安心して暮らせる地域社会の構築と持続的に成長できる仕組みづくりを町の基本理念とする中で、私が最も力点を置いた施策の一つが教育でした。当時は「生きる力」という言葉が中央教育審議会からも出されておりました。やがて10年後、20年後の社会を背負う高根沢町の子ども達が、まさに「生きる力」をいかに養っていけるかを模索する中で、私が現在のFonte(フォンテ)である不登校新聞を購読し始めたのです。当時もそうですが、今でも全国の首長でFonte(不登校新聞)を購読している人はあまりいないのではないかと思います。それだけ、どこの市町でも不登校の問題は教育の問題であって首長部局では報告を聞くぐらいだったと思います。不登校は毎年文科省が発表する数だけが注目されていたくらいだと思います。私の場合は、不登校新聞を購読していることもあり、他の首長より関心が深かったことは間違いありません。
2000年頃だったと思います。以前より高根沢町には適応指導教室がありました。しかし、それは教育委員会がある町改善センターという施設の一室にありました。元教員の方が尽力していただいているにも関わらず、来ている不登校生徒はわずか1~2名でした。(当時は40名近い不登校生徒がいましたが。)この現実を見て、これは子供たちが悪いのではなく、仕組み自体に大きな問題があるのではないかと感じました。そして、学校教育課の係長と適応指導教室についての議論を重ねたことを覚えています。
「学校に行けない子ども達の権利を守るのは町の義務」
適応指導教室、この名称を私は大嫌いですが、この名称に文部科学省の誤りがすべて表れています。学校にいけないのは現実に適応できない悪い子だから、適応できるように指導して学校に戻してあげる、という大人の傲慢さがプンプン臭う名称です。文科省は学校復帰を基本とした不登校対策を多額のお金をかけて20年以上にわたって実施してきたのですが、一向に成果が上がりませんでした。にもかかわらずその誤りに気付くことも出来ない。どうしてもそのことが腑に落ちなかったわけです。もともと、不登校になるには原因があります。しかもその原因は10人の子供がいればそれぞれに違います。その原因を探り子供たちに寄り添うということが一番大切であり、不登校した子どもを主人公として考えた時、学校復帰という選択しかないのはおかしいと思ったのです。何かしらの理由で学校に行けなくなった子どもたちは学ぶ権利、遊ぶ権利、生きる権利を失われている。それが義務教育年齢の子どもならば、彼らの権利を守るのは町の義務だと確信したのです。そしてこの考えを当時の加藤哲教育長に率直に話しました。加藤教育長は教育現場で長年のキャリアを積んだ方でしたから最初は戸惑いや疑問もあったと感じましたが、話し合いを続けた結果、何とか賛同を得ることができました。今だから正直に書きますが、加藤教育長も心からの賛同ではなく疑心暗鬼があったと思います。しかしその後、「ひよこの家」が実績を残し始めた時、誰よりも強い味方になってくれたのは加藤教育長でした。加藤教育長には今でも感謝しています。
「教育機関、行政機関から離れた場所を探せ」
そこで、当時の(阿久津)係長に話して、適応指導教室を学校や町の機関から一定以上離れた場所に探してもらったわけです。学校が嫌になって学校に行きたくなくなった子どもたちに、学校や教育委員会がある場所に来なさい、ということ自体、着物の下に鎧を着ているようなもので、そのような下心は簡単に子ども達に見破られてしまいます。
高根沢町はたんたんたんぼの高根沢と言われるほど美しい田んぼが広がっているのです。その中に町に貸していただける農家を一軒見つけてそこを改築させてもらい、高根沢町フリースペース「ひよこの家」として2003年9月、開所したのです。
「まず、地域住民への説明から始まった」
ただ、こういった施設が出来ると地域の方の中には心配される方も多いんですね。そこで、係長を中心に地域の方を一軒一軒訪問して、「ひよこの家」の説明をして理解を求めていきました。その甲斐もあって、「ひよこの家」は開所当初から地域の方がいろいろと応援してくださったのです。開所年のクリスマスパーティーにはその地区の区長さんが誰よりも早くお越し下さり、子ども達と一緒に参加してくださいました。農作物を持ってこられる近隣の方、おにぎりを持ってきていただける方など、今でも「ひよこの家」に協力していただける地域住民の方々がたくさんいらっしゃるのです。
「どこで学ぶかではない、何を学ぶかが大切だ」
中野謙作。この名前は銘記しなければならない名前です。施設は出来ても問題は運営でした。役所がやっても上手く行くはずがありません。子どもの学びや育ちについて地道な活動をしていた中野謙作さんには最初から様々なアドバイスをいただきました。その結果、「ひよこの家」の運営は、地域で活躍しているNPOの方と連携して行うという形を創ることができました。指定管理制度のように予算を渡してお願いするのではなく、行政が上でも下でもない、同じ目線で、主人公である子どもたちについて何が必要かを考えあえる官民連携の理想的な形で進めていきました。「ひよこの家」は農家を借り受けましたからそれこそ土間が広く囲炉裏があり、薪ストーブがあったりする、昔ながらの農家で「おばあちゃんの家に来た」という錯覚を覚えるくらい、誰もが来やすい場所でした。ある職員は、「ここで勉強ができるんですか?」と心配したほどです。私はいつも「どこで学ぶかが大事なのではない。何を学ぶかが大切なんだ。」と職員に話し続けました。形の上だけで無理やり学校復帰させても、終日保健室にいることでは何も学ぶことができない。数字の上では不登校が減っても、学ぶことのできない生徒が増えてしまうのだったら何の意味もないことではないのか。学校に行けないなら、学校でないところで学べる「場」を作る、遊んだりできる「場」を作ることが大切で、それがどこであろうと、本人に学ぶ意思があれば無理に学校に行かせなくても良いのです。それが「ひよこの家」となって具現化したと思っています。
中野さんには2003年に高根沢町の教育委員に就任してもらいました。今でも忘れ得ないことは、まだ無名だった中野謙作さんの教育委員選任同意を町議会に提出した時に「この中野というのは何処の馬の骨だ?」と質問されたことです。ひと昔前の教育委員は完全に名誉職であり、町議会のOBであるとか名士の方々が就任されていましたから、古い価値観の議員の方にはカルチャーショックであったのかもしれません。現在中野謙作さんは、一般社団法人栃木県若者支援機構理事長、厚生労働省委託事業とちぎ若者サポートステーションセンター長など、若者支援のために奔走されています。当時、引きこもりの青年のために、毎月五万円以上の電話代を自腹で費やしていたのが中野謙作さんでした。馬の骨の真贋を見分ける眼力が自分にはあったなと密かに自負してもいます。嬉しいことだと思います。
「行政の枠を超えた近隣市町からの通級」
この「ひよこの家」は高根沢町が設置した適応指導教室です。しかし、「ひよこの家」の評判が広がるに連れて近隣の市町からも「ひよこの家」に来たいという子どもが出てきました。町で設置している適応指導教室に町外の子どもを通わせることについては教育委員会でも議論していただきましたが、高根沢町では町外からの通級も可能としました。この時に「町の税金で運営していることは事実ですが、子どもに市町の境はありません。苦しんでいる子どもがいれば、たとえ他の市町の子どもであっても受け入れるべきです。」と強く主張してくれたのは、他ならぬ最初は慎重派だった加藤哲教育長でした。一番遠い子は、自宅から自転車を30分こいで駅まで行き、そこから電車に40分乗って宝積寺駅まで、さらに宝積寺駅から自転車に乗って30分かけて「ひよこの家」まで来る子どもさんでした。彼は結局、大雪の日でも一日も休まずに「ひよこの家」に通い続けました。実は、彼が「ひよこの家」10周年記念大会の実行委員長だったんです。彼の成長をみると「ひよこの家」を設置して本当に良かったと心から思えます。
「困難と思われた学校給食の導入」
今、生活困窮が社会問題となり国の施策にもなっておりますが、「ひよこの家」の開所当初も生活困窮問題が浮き彫りになりました。開所当初は数人の子どもが通っていましたが、昼食は各自、お弁当を持参するか、買ってくるようにしていたのですが、一人だけ昼食を取らない子どもがいたのです。よく聞くと、今でいう生活困窮している母子家庭で母親にお弁当を作ってもらう時間がないという理由で昼食を取らなかったのです。それを聞いた係長が「それならば学校給食をひよこに持って来れば良い」と思い、私のところにも話に来たのです。ところが、「ひよこの家」は狭い農道を通っていきますので給食車が通れない。それに衛生面から考えても難しいということでした。しかしそんなことで諦める係長ではありませんでした。学校給食センターとの話し合いを重ね、衛生面の対応を組み立て、議会をも説得して可能な形を作りましょう、ということになり、「ひよこの家」に学校給食が来るようになったのです。制度や規則があるから無理とあきらめるのではなく、子どもを中心に考えた時、必要であれば制度や規則を変えることが出来るのも行政の力の一つですから、係長はそれを見事に活用してくれたわけです。
「子どもの中から生まれた『学校復帰』という選択肢」
開所してからもう一つ、驚くことがありました。「ひよこの家」に来る子どもたちは何かしらの困難を有していることが少なくありません。そのため、スタッフはまず子どもたちに安心・安全を伝えていきたい、ということを念頭に置いていましたから、まず「ここにいればだいじょうぶ。自分の好きなことをすればいい。」と伝えるのです。勉強もできる、ゲームもできる、料理もできる、友達と話しもできる・・・・何もしなくてもいいから、と伝えていくことで、不登校で傷つき、自己肯定感が低くなった子どもに「安心」というベースができてくるのです。
徹底して「ひよこにいればだいじょうぶ」と子どもたちに伝え、安心できる場が出来てきた、と思っていた時でした。子ども達の一人から、「俺、学校戻ってもいいかなって思うんだ。」という言葉が返ってきたのです。子ども達の心に安心と安全を与えることで、子ども達の心に学校復帰という選択肢が生まれたのです。今まで文部科学省は(今でもですが)学校復帰を前提として適応指導教室を設置し、不登校児童生徒の学校復帰政策にどれだけの税金を投下してきたか。そうではないことを、「ひよこの家」の子どもが証明してくれました。学校復帰を前提としないことで、子ども達の心に学校復帰という選択肢が生まれたのです。それは学校に戻そうとする努力ではなく、子どもの心に安心を与えることで子どもの自己肯定感は回復し、学校に行くことも選択肢の中に生まれるという新たな発見でした。
「高校まで範囲を広げれば皆、学校復帰するという事実」
学校復帰のことでもう一つ話をさせてください。「ひよこの家」の子ども達を総じて考てみると、中学を卒業して働き始めた1名を除いては皆、高校へ進学しています。つまり、義務教育だけで不登校問題、学校復帰政策を考えるのではなく、高校まで広げれば、ほぼみんなが学校復帰をしているのです。義務教育だけで不登校を考えるから子ども達に無理な学校復帰を押し付けてしまう。であるならば中学校は行けなくても高校やその先までを視野にいれた支援を考えることが必要なのだと思います。
「子ども達の安心安全を守る=多様な学びの保障が求められている。」
「ひよこの家」が出来て10年を超え、85名を超える子ども達が卒業していきましたが、振り返ってみると、先ほどの10周年記念大会の実行委員長がその時に言った「不登校したからこそ、今の自分がある。」という言葉がすべてを集約していると思います。不登校というとどうしても否定的に取られてしまいます。それは学校に行くことが当たり前で、不登校生は学校復帰が当然、といった「大人の常識」が決めつけているからです。しかし子どもを主人公におき、子どもの目線で一つ一つをみつめていくと、学校だけでない多様な学びの必要性が浮き彫りになってきます。「ひよこの家」は始めから多様な学びを追求したわけではありません。不登校して学べない、遊べない子ども達が安心していられる場所、学べる場所を作ってきたことが結果的には多様な学びを広げることになりました。また、子ども一人ひとりにじっくりと向き合うことで、必ず子ども達がエンパワーメントできるということも今になって「ひよこの家」では日常のように行われています。ご存じのようにこれから訪れる超少子高齢時代を考えた時、今の子ども達を一人も失うわけにはいかない、と心底思うのです。「東京シューレ」や「ひよこの家」のような多様な学びが保障されることこそがこれからの子ども達には確実に重要だと考えています。
「ひよこの家」の歩みを振り返る時、今は天国にいる阿久津正さん、田内幸子さんに、この拙文を捧げたいと思います。